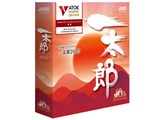ソニー「α1 II」は、2024年12月13日に発売された、ソニーのミラーレスカメラ「αシリーズ」の新しいフラッグシップモデル。高画素によるすぐれた描写性能と、高速・高精度AF&高速連写によるスピード性能を両立しつつ、従来モデル「α1」以降に培った高機能を惜しみなく詰め込んだハイスペック機です。従来モデルからどう進化したのか? を詳しくレビューしたいと思います。
最新鋭のフラッグシップモデルとして登場した「α1 II」
ソニーでは初となる「ミラーレスのフラッグシップ」として一世を風靡したのが、2021年3月19日発売の「α1」でした。今回レビューする「α1 II」は、それから3年以上の時を経てモデルチェンジを果たした後継機です。
そんな「α1 II」ですが、撮像素子には、従来モデルと同じ有効約5010万画素の積層型CMOSイメージセンサー「Exmor RS」を採用しています。
有効約5010万画素の撮像素子は従来モデル「α1」と同じ
画像処理エンジンは高い処理能力を持つ「BIONZ XR」で、これも従来モデルと基本的には同じです。したがって、得られる画像の解像性能も基本的に従来モデル「α1」と同じということになります。しかし、高画素モデル「α7R V」の有効約6100万画素に迫るほどの高画素を維持しているのですから、解像性能については「αシリーズ」なかでも、相変わらずのトップクラスだと考えて差し支えないと思います。
α1 II、FE 24-70mm F2.8 GM II、50mm、F8、1/160秒、ISO100、ホワイトバランス:オート、クリエイティブルック:ST
撮影写真(8640×5760、24.3MB)
常用感度も従来モデルと変わらずISO100〜ISO32000に対応しています。
「α1 II」の常用最高感度は従来モデルと同じISO32000
有効約5010万画素にして常用最高感度がISO32000というのは立派な高感度性能だと言えると思います。裏面照射構造の高い感度特性に、ギャップレスオンチップレンズ構造、シールガラス上のARコート(反射防止膜) などソニーが蓄積したセンサー技術と画像処理エンジン「BIONZ XR」を組み合わせたことによる好結果が引き継がれています。
下の作例は、高感度のなかでもよく使われるところのISO6400で撮影していますが、すぐれたノイズ処理技術が功を奏しているのか、高感度で撮影したとは思えないほどの高い質感と解像感が得られており、本モデルの実用性の高さがよくわかります。
α1 II、FE 24-70mm F2.8 GM II、70mm、F5.6、1/80秒、ISO6400、ホワイトバランス:オート、クリエイティブルック:ST
撮影写真(8640×5760、13.3MB)
従来モデルと同じ撮像素子と画像処理エンジンを採用する「α1 II」ですが、外観や操作性についてはいくらかの変更点が見られます。従来モデル「α1」と比較しながら、何がどう変わったのかを見ていきたいと思います。
まずはサイズ・重量から見ていきましょう。
α1 II
約136.1(幅)×96.9(高さ)×82.9(奥行)mm
約743g
α1
約128.9(幅)×96.9(高さ)×80.8(奥行)mm
約737g
※いずれも重量はバッテリーとメモリーカードを含む
「α1 II」は、従来モデルと比較すると幅と奥行きが少し大きくなり、重量も微増しています。機能の向上にともなってボディが大きくなるのは、デジタルカメラではよくあることでしょう。実際に使ってみると、両モデルでサイズ感の違いが気になることはありませんでした。
左が「α1 II」で右が「α1」。新モデルになってわずかにサイズと重量が増加しています。
幅と奥行きが増えた主な理由は、グリップ形状の変更によるものです。「α1 II」のグリップは「α1」に比べて適度に大型化していて、シャッターボタン周辺を含めて全体に丸みを帯びた形状になりました。個人的な感想ですが、この形状はとても手になじみ、ホールディング性能が向上しているように感じます。
ところで、前述の「α1 II」のサイズといい、新しいグリップの形状といい、どこかで見て聞いたことがあるように思っていたのですが、これはまさにスピードモデルの最新鋭機「α9 III」と同一、あるいは近いものですね。世界初のグローバルシャッター搭載機である「α9 III」の進化点を、「α1 II」も取り入れたということでしょう。
手前が「α1 II」で奥が「α1」。グリップの形状が変更され「α9 III」に近く(同一?)なりました。素直に握りやすく感じます
操作系統の集中するカメラ上部・背面側にもいくつかの変更点が確認できます。「α1」では「露出補正ダイヤル」だったダイヤルは、露出補正以外にも好みの機能が割り当てられる「後ダイヤルR」に変更。また、モードダイヤルの同軸下には「静止画/動画/S&Q切換ダイヤル」が搭載されました。静止画と動画を切り替える機会の多い、昨今の撮影スタイルでは重宝します。さらに、使用頻度の多い「C1」と「C2」のカスタムボタンは、背が高くなり、指がかりもよく押しやすくなっています。
これらの変更は「α9 III」と同じで、「α1」登場以降に改良された数々の操作性の向上を、積極的に取り込んでいる努力がうかがえるところです。
操作系統の集中するカメラ上部右側。従来モデル「α1」以降に培われた操作性の向上が盛り込まれています
背面の液晶モニターにも大きな改良が施されています。まず従来モデルの3.0型から3.2型へと大型化しているうえに、ドット数は約144万ドットから約210万ドットへと向上。可動方式は、比較的単純な「上下チルト式」から、横位置撮影でも縦位置撮影でも光軸を揃えることができる「4軸マルチアングル液晶モニター」に変更されています。
液晶モニターは、「α7R IV」以降の上位モデルに採用されている「4軸マルチアングル液晶モニター」。横位置でも縦位置でも光軸を揃えられます
こちらは、従来モデルの液晶モニター。横位置のみに対応した「上下チルト式」でした。当時はまだ「4軸マルチアングル液晶モニター」は存在していなかったのです
電子ビューファインダー(EVF)のスペックは約944万ドット/倍率約0.90倍で、従来モデルから変更はありません。元々ミラーレスのなかでも最高性能でしたので、これはフラッグシップモデルのEVFとして特に問題ないかと思います。フレームレートが通常の60fpsから最高240fpsの間で切り替えられる、動体撮影に特化した性能も継承しています。
従来モデルに搭載されていた高精細かつ高性能なEVFは、そのまま「α1 II」に継承されています
「α1 II」のEVF関連でうれしいのは、2種類のアイピースカップが同梱されていること。通常の「FDA-EP19」に加えて、より深い形状の新型「FDA-EP21」が付属します。「FDA-EP21」を使えば、外部からの光を効果的に遮断して視認性を高められます。
新しいアイピースカップ「FDA-EP21」を装着したイメージ。上の画像を比べるとより深い形状なのがわかるかと思います
操作性の向上という意味では、マウントの脇の押しやすい位置に新しいカスタムボタン「C5」が追加されたのも見逃せません。「αシリーズ」は各種ボタンに割り当てられる機能の幅が広く、自分好みの操作性を追求できるのが特徴ですが、その点も磨きがかかりました。
マウント近くの押しやすいところにカスタムボタン「C5」が追加されました
さらに、2個のバッテリーを同時に急速充電できるバッテリーチャージャー「BC-ZD1」が同梱されているのもうれしいところです。急速充電が可能なのはこのACアダプターが「USB PD(USB Power Delivery)」に対応しているため。最新のUSB環境で、フラッグシップモデルらしい充電環境がはじめから用意されているというのは、プロユースとしての資質をさらに高めている証しだと思います。
2個のバッテリーを同時に急速充電できるバッテリーチャージャー「BC-ZD1」が付属します
「α1 II」の撮影性能で注目なのは、やはりAF性能です。従来モデルと決定的に異なるのが、「AIプロセッシングユニット」の搭載。本ユニットは2022年11月25日発売の「α7R V」で初め採用された機能ですが、その後、数々の新モデルに搭載されて、その被写体認識性能の高さが好評を得ています。
「AIプロセッシングユニット」の高性能がわかりやすいのが、被写体認識対象の多さです。「α1 II」は人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機と数多くの被写体に対応。カメラが自動的に被写体を認識するオート設定も選べます。
「α1 II」は「AIプロセッシングユニット」を搭載しており、オート、人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機と数多くの認識対象を選べます
対して、「AIプロセッシングユニット」の登場前に発売された、従来モデル「α1」の被写体認識対象は、人物、動物、鳥の3種類のみ。AIによる学習量の多さと、骨格まで認識して予測する「AIプロセッシングユニット」の搭載の有無による、認識性能の違いは明らかだと言えます。
従来モデル「α1」の被写体認識対象は、人物、動物、鳥の3種類に限られます。個々の認識性能の高さにも、デジタルカメラならではの時代差があると言ってよいでしょう
「α1 II」の被写体認識性能は、対象が「人物」や「動物」の場合、従来モデルを比べて約30%向上しているとのこと。実際に使っていても、従来モデルより認識にかかる時間が短くスムーズであることを実感できます。
α1 II、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS、600mm、F6.3、1/1000秒、ISO12800、ホワイトバランス:オート、クリエイティブルック:ST
撮影写真(8640×5760、15.0MB)
さらに対象が「鳥」の場合、認識性能は約50%も向上しているとされています。カモを撮影した下の作例のように、ある程度の大きさがある鳥はもちろんのこと、小さな鳥でもしっかり認識してくれます。
α1 II、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS、600mm、F6.3、1/1000秒、ISO8000、ホワイトバランス:オート、クリエイティブルック:ST
撮影写真(8640×5760、13.9MB)
以下のカワセミの作例をご覧いただいたいのですが、画面全体がごちゃごちゃしているうえに薄暗い条件に小さな鳥がいる場合であっても、何の問題もなく正確に被写体を捕捉してくれました。まったく認識できなかったり、誤認識してしまったりということが多い条件のはずですが、この性能の高さには驚かされます。
α1 II、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS、600mm、F6.3、1/1000秒、ISO8000、ホワイトバランス:オート、クリエイティブルック:ST
撮影写真(8640×5760、14.3MB)
「α1 II」の連写速度は、電子シャッター時で最高約30コマ/秒、メカシャッター時で最高約10コマ/秒と、従来モデルと同じです。有効約5010万画素で最高約30コマ/秒なのですから、文句のつけようがない高速連写モデルであることに変わりはないと言えるでしょう。
「α1 II」で決定的にすばらしいのは、「α9 III」に続いて「プリ撮影」機能が搭載されたことです。
待望の「プリ撮影」機能が搭載されました
「プリ撮影」はシャッターを全押しする前にさかのぼって記録できる機能。「瞬間を逃さず撮れる機能」としてカメラメーカー各社がこぞって搭載してきましたが、ソニーはやや出遅れて2024年1月26日発売の「α9 III」で初採用でした。その機能が「α1 II」にも継承されたということです。
「プリ撮影」機能があれば、鳥が飛び出す瞬間など、人間の反応速度ではなかなか対応するのが難しい一瞬を撮ることができます。
α1 II、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS、600mm、F6.3、1/2000秒、ISO12800、ホワイトバランス:オート、クリエイティブルック:ST
撮影写真(8640×5760、13.4MB)
「プリ撮影」機能とあわせて注目してほしいのが、先にも少し触れた「α1 II」の被写体捕捉性能です。食いつきがよいだけでなく追従性も非常に高いので、高速で飛び立つカワセミに対しても、正確にピントを合わせ続けてくれました。
以下の3枚の連写作例は、「プリ撮影」を使って、カワセミが木の枝に留まっている状態から飛び立った瞬間をとらえたものです。飛び立ってから3コマ目だけでなく、さらに2コマ進んでもカワセミの瞳に正確にピントが合っていることがわかります。被写体を認識できてはいてもAFが追いつかないというカメラが意外に多いなか、「α1 II」の性能は驚異的と言えるのではないかと思います。
α1 II、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS、600mm、F6.3、1/2000秒、ISO10000、ホワイトバランス:オート、クリエイティブルック:ST
撮影写真(8640×5760、13.9MB)
α1 II、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS、600mm、F6.3、1/2000秒、ISO10000、ホワイトバランス:オート、クリエイティブルック:ST
撮影写真(8640×5760、14.1MB)
α1 II、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS、600mm、F6.3、1/2000秒、ISO10000、ホワイトバランス:オート、クリエイティブルック:ST
撮影写真(8640×5760、13.8MB)
この捕捉性能の高さは、前述の「AIプロセッシングユニット」の搭載が大きく影響しているものと思われます。ここにも「AIプロセッシングユニットの威力が!」といった感じで、従来モデル以降に培われた技術が積み込まれた意味は絶大だと思わざるをえないところです。
ピントが合いやすく、かつ追従性が非常に高いというのは、超望遠撮影時のフレーミングのしやすさにも直結します。今回の検証では、飛んでいる鳥を焦点距離600mmの超望遠で狙ってみましたが、素早く被写体を認識して正確に合焦し続けてくれるため、より容易にファインダー内に被写体を収めることができました。動きモノを撮っている人なら、この性能の重要性が理解できるのではないかと思います。
α1 II、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS、600mm、F6.3、1/1000秒、ISO6400、ホワイトバランス:オート、クリエイティブルック:ST
撮影写真(8640×5760、13.0MB)
最後に触れておきたいのが、有効約5010万画素の高画素で撮れることの便利さです。動きモノ(特に野鳥や野生動物)は画面内である程度小さく撮らざるをえないことも多いのですが、「α1 II」なら、約5010万画素の画素数を生かして、適切なサイズにトリミングしても十分な画質が得られます。以下の作例は、「α1 II」で撮影した写真をAPS-Cサイズ相当にトリミングしたもの。スピードモデルながらトリミング耐性にすぐれるのが「α1 II」の長所と言えます。
α1 II、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS、600mm、F6.3、1/2000秒、ISO10000、ホワイトバランス:オート、クリエイティブルック:ST
撮影写真(5616×3744、10.5MB)
「α1 II」を使ってみたところ、その動体撮影性能は、スピードモデルの最高峰「α9 III」に匹敵するか、あるいはそれに準ずると感じました。有効約5010万画素の高画素での撮影ですので、かなり健闘しています。画質(高画素)、AF、連写のすべてがハイレベルで、動体撮影機としての完成度は大きく向上したと評価してもよいでしょう。
「動体撮影用としてすべてを兼ね備えている」というと少し大げさかもしれませんが、本当にそのくらいの高性能だと思います。さすがフラッグシップを名乗るだけのカメラです。
そんな「α1 II」の価格.com最安価格は879,836円(2025年1月27日時点)。決しておいそれと手を出せる価格ではありません。ですが、ソニーは、円安が進む国内価格で何としても100万円以下を実現できるように努力したという話を聞きます。誰にも手に入れやすいカメラとは言えませんが、その性能を考えれば、この価格は良心的なのではないかと思えます。










![REGZA 40S25R [40インチ]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001672210.jpg)
![ROG Swift OLED PG27UCDM [26.5インチ]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001673920.jpg)
![LG gram Book 15U50T-GA56J [チタンシルバー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001673132.jpg)