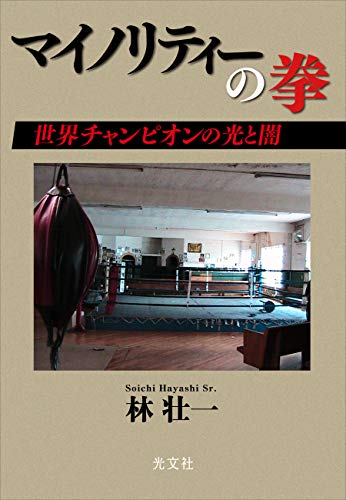17歳の少年が部活動の顧問による暴力を苦に自殺した「桜宮高校バスケ部事件」から10年あまりが経過した今年2月、加害者の元顧問が指導者ライセンス再発行を申請した。日本バスケットボール協会は5月になって申し出を却下したが、亡くなった少年を知る同校バスケ部OBの男性は、元顧問が再発行を望んだこと自体「腸が煮えくり返る思い」と語る。今なお暴力を根絶できず、死者を出し続ける日本の部活動とスポーツ指導の異常さを問う。
***
2024年5月9日、日本バスケットボール協会は、今年2月に指導者ライセンスの復権を求めていた小村基(58)の要請を拒否した。小村は大阪市立桜宮高校(※当時、現在は大阪府立)の元体育教師であり、同校男子バスケットボール部の顧問兼監督を務めていた男である。
2012年12月23日、桜宮高校バスケットボール部のキャプテンだった17歳の少年が、自ら命を絶った。制服のネクタイで首を吊るというショッキングな最期を遂げたのだ。小村はこの少年に対して連日、暴言・暴行を繰り返しており、キャプテンは追い詰められていた。
少年が死を選ぶ前日、小村は練習試合中のコートで彼を追いかけ回し、20発もの平手打ちを浴びせている。後に小村は傷害と暴行で起訴され、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡されている。2016年2月には、遺族が大阪市を相手に損害賠償を請求した民事訴訟で、東京地裁が市におよそ7500万円の支払いを命じた。その2年後には、大阪市が遺族に払った金額の約半分を小村に払うよう求めた訴訟で、大阪地裁が請求通りの4300万円あまりの負担を被告に命じている。
※こちらの関連記事もお読みください。
部活を辞めると必修単位が取れないスポーツ健康科学科
5月9日の決定後、筆者は桜宮高校バスケットボール部OBである谷豪紀をインタビューした。小村の犠牲者となった少年の2学年上で、同じポイントガードだった30歳のソフトウエアエンジニアだ。
都内で待ち合わせた谷は、朗らか、かつ爽やかな印象だったが、小村についての質問を始めると、途端に表情が曇った。
「小村がライセンス再発行を申請したことについては、腸が煮えくり返る思いです。卒業後、直接会ってはいませんので、実際に反省しているのかどうか分かりませんでした。ただ、小村も子を持つ身です。子供が成長すれば、自分が何をやったのかくらいは気付いているだろうと感じていました。でも、こちらの一方的な期待に過ぎなかった。風の噂でどこかでコーチとしての復帰を目指しているようなことは伝わってきましたが、いかに常識に欠けた人間でも、流石にそれは無いだろうと。ライセンス再申請の動きがあることは、ご遺族から伺いました……」
小村にも子供がいる。親であるなら、我が子の亡骸と対面した際の、遺族の気持ちを汲めるはずだ。
「高校時代、時々、休日に4~5歳の息子を連れてきていました。バスケットコートの後ろにある教員室で、遊ばせていましたよ。教師が空いている時間に部活動を見ているわけですから、指導者側も色々大変なんだろうなとは思います。でも、あの人たちにいい指導を求めるのは、そもそも難しかったですね。私は、制度自体に問題があったと見ています。
桜宮高校は思った以上に異質でした。チーム一丸となって一生懸命頑張る集団ではなく、管理された薄暗いイメージです。とにかく、小村は生徒を服従させたかったんですよ。指導者としての哲学や選手の心のケア、マネージメント理論等まったく無い人間です。声は聞こえるのですが、話が上手いわけでもないし、ボソボソした喋り方で、体育館の端までは通りません。また、相手に興味、関心を持たせられる語り口ではありませんでした」
谷がバスケットボールを始めたのは小学3年生の時だった。ガードとしてゲームメイクを担当し、小、中と所属チームでキャプテンを任された。強豪校で揉まれたいと、練習の厳しい高校を選んだ。
「桜宮には普通科と体育科とスポーツ健康科学科があって、バスケ部は一学年、10~20人くらいいました。8割がスポーツ健康科学科でしたね。実は大阪って、激戦区なんです。8校くらい強い高校があって、大阪でトップになるのは、かなりハードルが高かったです。桜宮以外の強豪校は私立で、推薦で背の高い優秀な選手を採るんですよ。だから桜宮にはサイズは小さいけれど、走力が売りみたいな子が多かったです。全国大会を狙えるなかでは唯一の公立ですし、エリート集団というよりも努力したいタイプが集まりました。
1週間に2~3限は、体育関係の授業でした。水曜日の5~6時間目に〈専門〉と呼ばれるクラスがあって、所属する部の練習に行って良いことになっていました。必修ですから、仮にバスケ部を辞めたら単位を落とすことになります。他の部に移る選択肢も、あって無いようなものでした」
自分で創意工夫する発想を奪う指導
谷が在籍中、桜宮高校は1・2年生時のインターハイ、2年生時のウィンターカップと計3回 、大阪代表として全国大会に出場している。それは一見、成功とも映る。しかし、当然のことながら小村が教師として適切な人間教育を施していたのか? という疑問が湧く。
「小村の下にいれば、思考力はまず伸びません。入学時より間違いなく下がりますね。一方で、心肺能力は上がります。同じ作業を何回もすることによって、操作に慣れる部分もあります。筋力もついたとは思いますが、適切な休息が無かったので、効果的じゃなかったです。
朝は1~2時間、放課後は21時くらいまで、土日祝日は朝から晩まで練習でした。年間を通した休みは3日くらいでしたよ。“勤続疲労”というか、常に故障者が各学年に2名はいました。そんな感じだからか、皆、あんまり身長が伸びないんですよ。高校生年代って、きちんと栄養を摂って休めば、まだある程度は背が伸びますよね。ですが、あの日常で身長が伸びた人は1学年に2人いるかいないかでした」
小村の指導とは一体どんなものだったのか。
「相手に何かを伝えるっていうスタンスが、まるで無いんです。桜宮高校の体育館はバスケットコートが2面あります。男子コートと女子コートで、その間に監督用のごつい椅子や机を並べて、いつもドーンと座っていました。選手を諦めさせてマネージャーに転向させた人間を、常に横に立たせているんですよ。小村がボソっと何か言ったら、マネージャーがチーム全員を集めて、監督の指示だと告げる。とはいえ、単にその日の気分で言葉を発していただけでした。
正直に言うと、よく分からない大人でした。小村はパスには自信があったのか、時々、ポイントガードのポジションから、選手を動かしてパスを見せることを手本としてやっていました。手練れていますが、あくまでも監督を相手に遠慮した高校生を相手にしたシチュエーションですから。シュートやドリブル、ディフェンスなどの技術的な部分を教えることはなかったです。口で言っているだけだから、生徒には分からないんですね」
日本体育大学を卒業した小村だが、バスケットボールの本場アメリカや、日本より格上のアジア強豪国のコーチングは学んではいなかったのか。
「そういう研究をするような人間ではなかったと感じます。そもそもバスケって、シュートが入らなければ勝てないわけですよ。パスをグルグル回していたって、得点にはならない。勝利にも結び付かない。桜宮高校は歴代、セットオフェンスが無茶苦茶下手でした。
今振り返れば、シュート練習が圧倒的に少なかった。自分で創意工夫して、こういうクラッチショットを打ってみたら面白いんじゃないか、みたいな発想さえ奪ってしまう指導でしたね。監督の言うことだけを守っていればいい、逆らうなら試合には出さない、あるいは暴力で口を塞ぐ。恐怖でがんじがらめにして、必死で事に向かわせるのが小村のやり方でした」
筆者はNBAや、米国の小、中、高、大学のトレーニングを目にしたことがあるが、いかなる年代においてもコーチたちは「自分の頭で考えたうえで判断すること」を選手に求めていた。
「私も当初は、監督に従えばいいのだという思考になっていました。パス練習にしても、何千回もやらされれば、10代のなかでは高いレベルになるかもしれません。でも、あの高校から日本トップのリーグで活躍できるまでに育つかと言ったら、そんな選手は一人も出ません。やらされるだけの練習ですから。手っ取り早く高校年代で結果を出すのであれば、選手一人一人に向き合わずに、単なる駒として服従させる方が楽だったのかもしれませんね。
私は1年次のインターハイが終了した時点で、ベンチ入りしたんです。でも、その後、何かが気に入らなかったらしく、『ヘラヘラしている』だの『ふざけている』だのと評価され、外されました。指導者と合わなかったという思いは、ずっとありました。でも、部を辞めてしまうと、学校も辞めなければならないので、それだけの理由で耐えていましたね」
高校生活の目標が「死なないように毎日を乗り切る」
小学3年生だった谷がバスケットボールに関心を持ったのは、1996年にドラフト1位でNBA入りしたアレン・アイバーソンに魅了されたからだ。身長183センチと、世界一のリーグではかなり小柄なガードだったが、1999年、2001年、2002年、2005年と4度の得点王に輝き、2001年にはリーグMVPも受賞している。
「高校時代はアイバーソンのプレーを真似てみたいとか、NBAのようなバスケをしてみたい等と、考える余裕すらなかったです。ただ単に耐える。一日を終える。それだけでしたね。今日をどう乗り切れるか。1年生の中間くらいから、『死なないように毎日を乗り切る』がテーマとなりました。そもそも、自分のやりたかったバスケが何なのか、振り返る時間すら持てないんです。
私は小村から、そんなに殴られていない方です。殴られる生徒と殴られない生徒って分かれるんですよ。小村の気分もありますしね。ルーズボールに飛び込まない、本人がやっているつもりでも、指示どおりにディフェンスをやっていない生徒は、問答無用で殴ったり蹴っ飛ばされたりします。さらに、小村の中で殴りやすい子、殴りにくい子っているんですね。“はい、はい”と言うことを聞く、健気なタイプは殴られます。それは、自分が率いる組織を都合よく動かすため、恐怖を植え付けるためなんです」
――そんな調子では、好きだったバスケットボールが嫌になってしまったでしょう? 筆者の問い掛けに、谷は深く頷いた。
「バスケが好きだという気持ちが、どんどん無くなっていきました。高校時代は、早く解放されたい、もしまたスポーツをやるなら個人競技がいい、ロードバイクでもやってみようか……なんて考えていましたね。実際に高校卒業と同時にバスケは辞めましたが、大学時代や社会人になったばかりの頃は、それこそ小村に嫌味を言われたり、ビンタをされたりする夢を頻繁に見ていました。
でも、最近見る夢が変わってきました。もっときちんとバスケをやりたかったなという気持ちになったのは、この1年くらいなんです。中学校時代に活躍して、バスケが楽しかった頃の夢を見たりしますね」
18歳で高校を卒業し、現在30歳の谷は、10年以上も過去に苦しめられたのである。
(つづく)