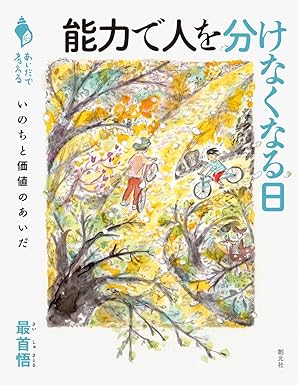ジャニーズにだけ詳しくてもジャニーズは語れない。
これは僕自身が、ジャニーズをはじめ好きなものについて語る仕事をし続けてきた上で、自分に言い聞かせていることである。もちろん、ジャニーズに限った話ではない。「好きな相手しか見ない」というのは、一見、真摯な態度にも見えるが、その実「好きな相手“も”見えていない」ということである。どんな人間も物事も、社会の中に存在している。その他の人や事象との関係性なしにその本質を捉えることはできないのだ。
12月に『夢物語は終わらない ~影と光の“ジャニーズ”論~』(文藝春秋 2024年)という書籍を発売したので、今年は僕にとってこの本の執筆の1年だった。創業者の性加害が大きな社会問題となった中で、ジャニーズだけを見つめても問題や事務所の本質が見えてこないという性質はより強まった。そこで、この本の執筆にあたり、思考の背景になった本を紹介したい。直接引用をした参考文献ではないが、普段の読書の中で出会い、思わぬところで自分の思考の手助けをしてくれた本たちである。

『敗者としての東京――巨大都市の隠れた地層を読む』(吉見俊哉・筑摩選書 2023年)は、東京を、家康・薩長・米軍によって3度占領されてきた“敗者”だと捉えた東京論である。東京を敗者として捉え直すという発想自体が慧眼だが、その意味では代々木に存在した米軍家族住宅エリアを含む施設、ワシントンハイツは敗者の街の中にできた勝者の街ということになる。
ワシントンハイツで暮らしていたジャニー喜多川が、近所に住んでいた少年たちと作った野球チームがジャニーズ事務所の始まりになるわけだが、ジャニー自身は日本で空襲の被害にもあっている。つまり、その勝者の街の中で集った敗者たち――という何層にも重なった背景の上にジャニーズ事務所は誕生した。善と悪、芸能界と芸事、大人と少年etc.ジャニーズ事務所が様々な境界線の上にある特異な存在であることは拙著の主張のひとつだが、その誕生が“敗者の街・東京にできあがった勝者の街に集った敗者たち”によるものであることは、非常に示唆的である。
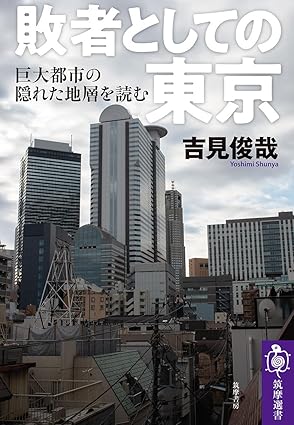
昨年から来年にかけて個展が全国を巡回している絵本作家の荒井良二。僕は3つの会場をまわったが、そこで手に取ったのが『ぼくの絵本じゃあにぃ』(荒井良二・NHK出版新書 2014年)だ。この本の中で、荒井は子どもを「未来の大人」と捉え、自分たち大人を「かつての子ども」と捉える考えに至ったことを綴り、こう述べる。
「子どものために」描くということは、自分も含めた「過去・現在・未来に存在するすべての子どもたちのために」描くことだとわかったのです(『ぼくの絵本じゃあにぃ』、NHK出版新書、2014年、55~56頁)
子どもと大人の境界線をなくす発想。実はこれはタレントを“永遠の少年たち”にしようとしたジャニーズの世界観とも親和性が高い。フランスの詩人・ボードレールが「天才とは意のままに取り戻せる幼年期にほかならない」と語っていることを踏まえれば、荒井もジャニーズのタレントたちも天才ということになるし、荒井のこの思考は「すべての天才たち」に向けて絵を描いているとも捉えられるものである。

だが、少年性を押し出すことは、過度にポリコレ化したこの社会の中で批判の対象となりうる。その少女の場合の例が『性と芸術』(会田誠・幻冬舎 2022年)で詳述されている。
四肢が切断され首輪をつけられた裸の少女を描いた会田誠の『犬』。展示に対して抗議活動も起きたこの絵に関して会田誠自ら解説する本である。
「ジャニーズはアート」というのは拙著の主張のひとつで、批判をあびたコンサートの演出と会田誠の『滝の絵』との類似性などにも触れている。アートにおける性的表現がどこまで許されるかという問題に対しては議論がつきないが、この本はそこに大きな思考の手助けをくれる。
特に会田が『犬』を批判する人に向けた「『この世の表現はすべて政治的なキャンペーンのポスターみたいなものだ』と思う病気に罹っている」という主張は、近年あらゆるエンターテイメントに対して“正しさ”を求める人々に突きつけたい一言でもある。また、美術家が作品を通じて行う批評は、対象が自らにも向く「自己批評」「自己解剖」を含めなければならない――という会田の主張は、ジャニーズの世界では拙著で紹介した井ノ原快彦による舞台が体現していることを付記しておきたい。
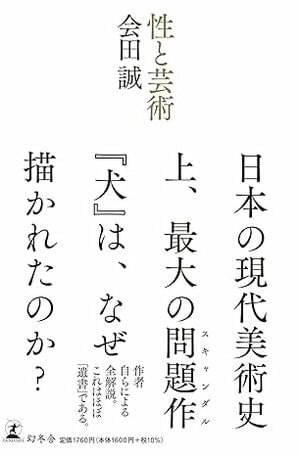
『小山田圭吾 炎上の「嘘」 東京五輪騒動の知られざる真相』(中原一歩・文藝春秋 2024年)は、2021年の東京オリンピック開会式の音楽担当を引き受けた小山田圭吾の“障害者いじめ”の炎上騒動を追った1冊だ。犯した罪が犯罪にならなかったときに、人はどれほどの罰を受けるべきなのか――。もちろん、罪の種類は違うが、ネット上で炎上し、マスメディアでも批判の言葉が溢れていく中で、“加害側”は事実ではないことに対する弁明までできなくなっていく状況はジャニーズ事務所にも近いものを感じた。
小山田と小沢健二の2人は芸能界に対する反発があったという証言もあり、拙著でも疑義を呈した日本のエンターテイメント業界独特の“本来、芸事を追究していればよかったはずの人々が、芸能界にも足を踏み入れなければいけないことで起きる歪み”がこの騒動にも表れているのを感じた。普段インタビューする側にもされる側にもなる自分としては、“切り取られ時代”の言葉の出し方や、載せる側の責任にも思考を巡らせる1冊だった。

冒頭に記した新刊では、僕自身の話も挿入しており、特に受験戦争に10代の時間の大半を捧げるうちに、ジャニーズJr.オーディションを受ける頃には事務所の求める“少年”ではなくなってしまっていたことへの大きな後悔を綴った。『能力で人を分けなくなる日 いのちと価値のあいだ』(最首悟・創元社 2024年)の「学校は『より速く、より高く、より強く』というオリンピックの標語そのままの価値観をみんなに要求している」という言葉に、自分は能力主義の社会に絡め取られて生きてきてしまったのだ、と改めて感じた。最首と中高生との対話で構成された1冊だが、最首はもちろん、10代の少年少女たちのピュアでありながらも先駆的な意見にも発見が多くあり、彼らが生きる社会が、表題通り“能力で人を分けない”ものになることを強く願った。