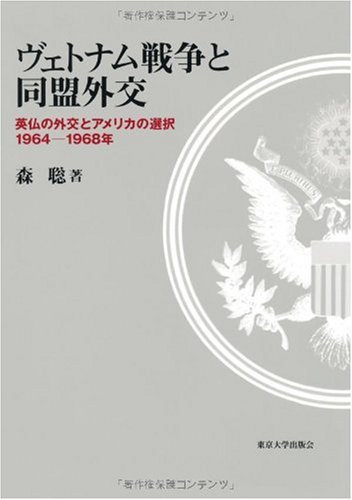【KCS|ROLES特別公開フォーラム】無極化する世界はどこへ行くのか―ウクライナ戦争とイスラエル・ハマス戦争の行方―(2)
※2023年12月6日開催の講演内容をもとに、編集・再構成を加えてあります
細谷 続きまして田中浩一郎先生にお話しいただきます。田中先生は慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科の教授であり、皆さんよくご存じの通りイランなど西アジア・中東がご専門です。イスラエル・ハマス戦争が始まってからも多くのメディアでご発信をしておられます。
多様でアクター固有のロジックが前景化
田中浩一郎 ご紹介ありがとうございます。私からはウクライナ戦争とパレスチナ問題ないしはイスラエルとハマスの間の紛争を個別的に見ながら、この二つの出来事に通底する要素を拾いながら皆さんの大局的なお話と繋がっているところを考えたいと思っております。
この二つの出来事のどこが通じているか。一つは固有のロジックの前景化が挙げられるでしょう。もう一つは戦闘を行う能力構築のあり方、具体的に言えば兵器供給の「上流と下流」という関係が大きく変化しつつあることです。

冷戦後、中東には地域紛争が増えました。その背景にあるノンステートアクター(非国家主体)の台頭というキーワードに、我々はもうずいぶんと長いこと向き合っています。危機が紛争に至るには、その当事者に必ず何らかの意図があります。国家であれノンステートアクターであれ、それぞれに固有のロジックがあるわけですよね。それが我々の感覚において認められるかどうかはまったく別です。これは価値の問題ですので、良い悪い、正しい間違っているということをここで言うつもりはありませんが、それぞれのロジックを持っていることは変わりません。
ウクライナ戦争を続けるロシアが「ルースキー・ミール(ロシア世界)」や小泉先生のお話にあった「多極化」を主張しているのと同様、イスラエルとハマスの紛争でも、イスラエルにはシオニズムというロジックが働いている。現状のイスラエル政府は民主主義によって成り立っていますけれども、国家の建設はシオニズムによって成り立っていたわけです。
ノンステートアクターであるハマスには、雑駁な表現ですがメディアに「イスラム主義」として紹介されているものがある。この紛争にいろいろな形でかかわっているということで非難を集めるイランにもイランでロジックがあるし、たとえば今、イランはハマスやヒズボラ、フーシ派などを包摂する「抵抗の枢軸」というグルーピングを一生懸命作っているとされますけれども、これも反米陣営を強化するロジックになるわけですね。
ウクライナに目を戻すと、イランはロシアに対しても有形無形の支援を行っているということでまた非難を浴びているわけですけれども、これは歴史的な射程でみると、非常に変わった状況です。イランは基本的にロシアが大嫌いです。イデオロギー大国としてのソ連のみならず、ロシアに土地を奪われた、日本の北方領土どころじゃない広大な土地を19世紀に奪われたということで、大嫌いなわけです。しかしそのイランが、ウクライナ戦争では兵器の供与であるとか、国連総会での議決の際にロシアの側に立っている。これはイランを長く見てきた人間からすると、まずあり得ないはずの状態です。
これら個々のロジックを各主体が抱えたうえで、どこと組むか、どこと敵対するか、衝突するかという合従連衡が起きているわけです。これはいったい何なのか。昨日の敵は今日の友か、敵の敵は味方というロジックなのか。あるいは地政学的な利得を考えると、ほかのことはすべて脇に置いて組めるところと組むという場当たり主義的なものなのか。いずれにせよ、本日のテーマである無極化の、一つの表れなのかもしれないと思っています。
次に能力の方の話をします。第1次世界大戦期の経緯を振り返ってもそうですけれども、中東というのは長い間、大国の草刈り場でした。その代わり、冷戦時代は大国の陰や傘下に置かれてきたため、それが地域にある種の安定をもたらしていたとも考えられます。その分、兵器体系はそれぞれの“親分”から“下賜”されたものを購入するというパターンがはっきりあって、東西陣営の東側に属していたイラク、シリア、リビア、一時期までのエジプトなどは常に東側の兵器体系を備えてきた。それ以外の国は西側になるわけですが、いまのイランでさえ1979年のイラン革命までは親米でしたので、アメリカの最新鋭兵器を入れていました。去年(2022年)「トップガン」の2作目が公開されましたけれども、あの中に出てくるF14トムキャットをアメリカ以外で唯一保有しているのはイランなんです。ほかには世界のどこにもなかった。そして今でも見事に運用しています。
中東の国々が東西に分かれ、兵器を輸入することでそれぞれの陣営の超大国に依存する構図は、冷戦終結後も一定程度は引き継がれました。ソ連崩壊後のロシアを超大国と位置付けるのは難しいですが、兵器体系は一朝一夕に変えられるものではありませんし、武器供給能力について言えばロシアの力はやはり大きい。ところが、ここに転機が見て取れます。2020年の第2次カラバフ紛争、ともに旧ソ連構成国であるアルメニアとアゼルバイジャンが衝突したこの紛争に、いつの間にか中東の国が兵器を供与する側になっていた。トルコのUAV、つまりドローンです。アゼルバイジャンが使用したトルコ製「バイラクタル」が大きな戦果を上げたのです。
ロシアに対してもイランからUAVが提供されています。よく知られているのが「シャーヘド」「モハージェル」という二つのシリーズですが、「アーラシュ」というもう一つ別のシリーズも提供されているとの見方もあります。さらに厄介なことには、今後ひょっとすると弾道ミサイルがイランからロシアに提供される可能性もある。イランの弾道ミサイルの原型は旧ソ連なんですよね。かつてロシアが開発したものがイランで長期間モディファイされ独自の形式として発展し、今度はロシアに提供されるということになると、かつての「片方が兵器供給の上流で片方が下流」という関係はもはやなくなってきているということが、さらに鮮明になるでしょう。
ハマスの戦いぶりを見ても、賞賛するつもりもテロ攻撃を是認するつもりもまったくありませんが、彼らの戦いぶりは大国の兵器に依存しない。イランなどからの技術提供があったとはいえ、自らの手で作り上げたもので近代兵器の粋を集めたイスラエルと戦っているわけです。かつては超大国からの兵器で軍や戦闘能力を維持した中小国・非国家主体が、いまは他に頼らずに能力を持つ。これもゲームチェンジャーだと言えるでしょう。
もちろん幸いなことに、その能力は近代兵器に較べたら小さいものです。大量破壊兵器と呼べるような代物ではありません。しかし構図はガラッと変わり、ノンステートアクターが素直に大国に従うような状況ではなくなってきている。これもまた無極化のひとつの表れではないか。このあたりがウクライナ戦争と中東におけるイスラエル対ハマスの紛争を繋ぐ糸なのではないかと思うわけです。
細谷 田中さんありがとうございます。6月の東大でのシンポジウムでは大学発のシンクタンクで何ができるのかを議論しました。それがまさにここで実現しているということで、私も大変嬉しいところです。今日のような形で社会に還元して行くのは大学の使命でもあるのだろうと思います。
最後のスピーカーは、慶應義塾大学法学部教授であり、戦略構想センター(KCS)副センター長をしていただいている森聡さんです。森さんにお話しいただくのは、これまでの先生方のお話にあったような地域の情勢を受けて、ウクライナにも中東にもどちらにも深くかかわっているアメリカはいまどういうことを考え、何をしようとしているのか、これを俯瞰的にお話しいただければと考えております。
指導力を持つ国が分野ごとに複数存在する秩序
森聡 私の方からは3点ほど問題提起をさせていただきます。
まず一つ目は、「無極化」「多極化」というキーワードが出てきましたけれども、「極」とは何なのかということです。これからの国際政治を「極」で見て行くことの妥当性を考えたいということですね。
それから2点目と3点目はアメリカに関する問題提起です。
2点目はさきほど小泉先生からも抑止力というお話がありましたが、いまアメリカに問われているのは欧州、中東、東アジアという三つの地域を睨んでいるアメリカのセキュリティ・ブランケット(安全保障の及ぶ範囲)は十分に広いのか、信頼に足るものなのかということです。
3点目は、いままで追求してきたリベラル覇権秩序というものは果たしてアメリカにとってペイするのかということ。アメリカ国内でも焦点になっている問題ですが、これについては二つの対照的な議論が出てきていて、これがおそらくトランプとバイデンのリマッチにも影響する。
この3点について、ポイントをいくつか述べさせていただければと思います。

まず1点目の「極とは何か」ですが、私は現在の国際社会について、「多極化はしていないが無極化はしている」という見方をしています。
「極」に関するアカデミズムの伝統的な定義は、国家が目標を追求するために動員できる資源としてのパワーというものです。これを捉えるには軍事費やGDPといった指標がよく使われます。こうした一般的な指標ではアメリカが群を抜いていて、中国がそれを追いかけ、三番手、四番手以下がぜんぜん規模が小さい。こうしてみると単純に実態としてどこに多極があるんだという議論が成立し得るということですよね。
では「無極化はしている」というのはどういうことかというと、いま申し上げた資源としてのパワーの分布がどうかという問題がある一方で、大国が自分の望む結果を出せるか、情勢をシェイプできるか、要するに影響力としてのパワーがどれほどあるのかという別の問題もあるのです。資源としてのパワーでは群を抜くトップのアメリカも、影響力ということでは、確実に低下しているということが言えるだろうと思います。中国もロシアも他の国々も、いろいろな形で積極的に影響力を行使するようになった。もともと万能な影響力はありませんが、アメリカが思うように国際情勢をマネージできる時代ではなくなってきた。ドミナンス(支配的立場)という言葉をアメリカ人はよく使いますけれども、ドミナンスで自分たちの望む方向へと国際情勢を引っ張っていく力は衰えたという意味で、やはり「無極化」してきていると言えるんじゃないかと思います。
それでは、そもそも現代国際政治を「極」で見て行くことの妥当性はどうなのか。ここでも、マルチセンター的な多国間協力の重要性が高まっています。背景には、たとえ地域紛争であってもグローバルなインプリケーションを持つという、危機の時代相の変化があるでしょう。たとえばロシア・ウクライナ戦争は、アフリカや中東を中心に食料安全保障の問題を提起しました。イスラエル・ハマス戦争が激化すれば国際エネルギー需給の問題になりますし、台湾問題が火を噴けば半導体供給の問題になります。無論、パンデミックや気候変動も国家の社会・経済に大きなインパクトをもたらします。
そういう危機の時代に試されるのは何かというと、単に国防予算やGDPが大きいかどうかということだけではなく、国家としてのレジリエンス(強靭性)です。危機が起こった時に、その分野における様々な多国間協力のようなものを――今までだったらアメリカが旗をふって、アメリカの下に国際協力を糾合するわけですが――アメリカ以外にも分野ごとに指導力を発揮できる国が複数いて、それらの国が国際協力を主導して、攪乱的な影響を緩和できるかどうかが問われている。これを米アメリカン大学教授のアミタフ・アチャリアは「マルチプレックス(複合型)・ワールドオーダー」という言葉で表しています。要するに機能分野別に協力とか求心力を発揮する国が複数あって、アメリカ以外にもそうした国がいるということを、1945年から2017年までに結ばれた3万3104件の条約を対象に、「インタラクション・キャパシティ」といって、協力関係を形成できる・している国がどれだけ増えているのかということを分析しています。これによると、依然としてアメリカはかなりの求心力を持っているけれども、アメリカ以外の国も相当程度諸外国を糾合する力を発揮しているということが示されている。
つまり、機能分野別に、多層的に国際協力のネットワークを作り上げて、多様な影響力を発揮する国が、色々な地域に分布している国際秩序というものを構想し得るのではないかと思います。
2点目、アメリカのセキュリティ・ブランケットの問題をめぐっては、様々な事件を通して、なんとなく心もとないという印象を広げてしまっている。特にロシア・ウクライナ戦争を見ていると、「直接介入をしない」「エスカレーションを避ける」というアメリカの姿勢は、「もしかすると結局、核保有国とは戦わないのではないのかこの国は」というふうなイメージを蔓延させてしまっている。これはおそらく台湾であったり、東アジアであったり、我が国であったりに一抹の不安を覚えさせていて、アメリカのセキュリティー・プロバイダーとしての信頼性が揺らいでいるという状況があるように思います。アメリカはあれだけ突出した武器援助をやっているので、パワーそのものはまだまだあります。ただ、その使い方がずいぶん変わってきた。それはやはり国内政治の影響が出てきているということなのではないかと思います。
そこで3点目、アメリカで国内政治の一大テーマともなっている「リベラルな覇権秩序はアメリカにとってペイするものなのか」という問題が出てきます。これは、その根底にはさらに二つくらい問いがあります。
一つは「秩序は手段なのか目的なのか」という問題です。もともと大国というのは、自国の安全と繁栄を推進するために、自分にとって好ましい秩序を作ろうとします。しかし、その秩序を維持しようとして、たとえば武力介入などを繰り返すうちに、いつの間にかコストがどんどん大きくなって、秩序を支えることが自分を弱らせる状況を招いてしまう。過去ではこういう局面になった時には、アメリカというのは戦略の調整を図ったりして一生懸命立て直すということをやってきたわけですけれども、それをやる力が、いま分断されているアメリカの中で弱ってしまっています。秩序を支えるコストが大きくなった時の戦略の調整をやる能力が、一国主義が頭をもたげてしまった結果、国際主義とぶつかり、十分な調節能力を発揮できなくなっているということがあるのだろうと思います。
根底にあるもう一つの問いというのは、アメリカの安全と繁栄というのは、他国の安全と繁栄とどこまで繋がっているのかという問題です。これがたぶん、一国主義と国際主義を分けるところです。自国と他国の平和と繁栄が繋がっていると見る、積極的な対外関与を提唱する国際主義は、民主党でも共和党でも依然としてワシントンの主流派でしょう。ただ、いや他国は他国だろう、と他の国は自分で自分を守るためにもっと血と汗を流せという考え方を持つ人たちが、以前よりもかなり増えてきた。そうすると、インド太平洋とヨーロッパ諸国のアメリカの同盟国というのはあれだけ金持ちなのになんでアメリカの納税者のカネを使って守らないといけないんだというような主張や議論が通りやすくなる。そんなところの面倒を見ないで、アメリカはアメリカ自身にもっと投資すべきじゃないかと、「アメリカファースト」の根底にはそういう考え方があるのは間違いないのではないかと思います。
ということで、「リベラル覇権秩序」ないし「リベラル国際秩序」と呼ばれるものをワシントンのエリートたちが絶対視して、コスト度外視で追求してきた結果、特に介入主義のツケがアメリカの一般の人たちにまわってきて、こんなものはもう受け入れられないという人たちが民主党の中にも共和党の中にも出てきている。これが、おそらくトランプに一層顕著に出ますし、バイデンにもいろいろな形でちらちら出ていると思います。バイデンにもトランプにも、国内の一国主義的な考え方を持つ人たちにアピールするような政策をやるんだ、あるいはやらざるを得ないんだという考慮が働いている。度合いとしてはやはり共和党、特に保守派に一国主義が強いと一般的には言える。従来のリベラルな国際主義とはまったく異なる一国主義的な重商主義の考え方に立ってアメリカが外交と防衛をやる、経済をやるという時期が到来しつつあります。
2024年の大統領選もそうですが、バイデンが再選されてもされなくても2028年には「ポスト・バイデン」の候補が民主党から立ちますし、「ポスト・トランプ」も共和党から出てくるわけですが、そのとき両党の大統領候補は一国主義の世界観を持っているのかということが問題になる。しかも皮肉ですが、海外で国際秩序のために色々なコストを払えば払うほど、それに対する反動も国内で大きくなってしまう。国内主義と国際主義の逆説で、世界で頑張れば頑張るほど国内でそれに対する反動が生まれてくる力学が出てくる。
アメリカがリベラル覇権秩序を支えられなくなった時に、日本のような国がどういう秩序を目指すべきでしょうか。私もふさわしい表現を探しているのですが、天井は「リベラルな国際秩序マイナス介入主義」と低くなり、床は「ウェストファリア体制(主権国家の相互承認と並存)プラス国連憲章」と少し底上げしたところ、その間のどこかに、何か広い、グローバルサウスも含めて西側とは違う国々が新しい様々な機能分野別の協力を通じて成長、発展の原資を共有し、国家としての強靭性を高めて経済・社会の発展を担保していけるような空間を作り上げていくことを検討すべきだと考えています。
ヨーロッパにはこういう考え方がすでに出てきているようでして、このあたりは細谷先生にぜひお伺いしたいと思います。大国間秩序が大きなウェイトを占めるので、オルタナティブな国際秩序にいきなりシフトするとは思いませんけれども、仮説として、そういう見通しがあってもいいかもしれません。
リベラルの「利他性」を攻撃するポピュリズム
細谷 ありがとうございました。森さんの仰る「リベラルな国際秩序-介入主義」というのは私も賛同します。やはり近年は、自分たち以外の人のためにお金を使うことのハードルが上がっているんだろうと思うんです。不寛容、アカウンタビリティ(説明責任)が厳しくなっていることで、国内の問題解決に使えという圧力がポピュリズムからかかってきたときに、リベラルな国際秩序が想定しているような理性的かつ利他性を備えた構想が難しくなる。
もちろん、これはある意味では100年前のウィルソンの頃から変わらないわけですよね。ウィルソンは国際連盟を作り、アメリカがそこで一定の貢献をしようとしたけれども、アメリカの議会も国民もそれを求めていなかった。こうした国際主義と国内主義の逆説が、再び国際秩序を揺さぶっています。今日、森さんがお話ししてくださった内容は、池内さんや小泉さんも執筆者に名を連ねる『ウクライナ戦争と世界のゆくえ』(東京大学出版会)の中で、森さんが「ポストプライマシー時代のアメリカによる現状防衛」としてお書きになったこととも重なる内容ですね。
さて、今日の議論を伺っていると、おそらくウクライナ戦争とイスラエル・ハマス戦争を繋げる、もう一段大きな俯瞰の視点が必要なのだとの思いを強くします。国際社会が新しいステージに移ってきていることを前提に、我々もいままでの議論を膨らませる必要がある。 [(3)へ続く]
※(3)は2月28日公開予定です