ソーシャルゲームが大流行する「薄気味悪さ」
ゲームジャーナリスト 新 清士

パソコンや携帯電話で手軽に遊べる「ソーシャルゲーム」が世界的に大流行している。成功の理由は、友人と交流する「ソーシャル機能」や基本料が無料の「フリーミアムモデル」などいくつかあるだろうが、実際に遊んでいると、それだけでは説明しきれないある種の「計算」も感じる。今回はそれを「痛みポイント」というキーワードで読み解いてみたい。
米ソーシャルゲーム最大手のジンガが2010年12月に公開した街づくりゲーム「CityVille」は、2カ月足らずで世界で1億人の登録ユーザーを集める成功を収めた。住宅や農園、商業施設などを作りながら自分の街を育てていく内容で、クリックだけの簡単な操作ながらゲームの完成度は高い。グラフィックスもよく作り込まれていると評判を集めている。
実際、筆者もこのところ夢中になって遊んでいる。ソーシャルゲームはもはや低予算で短期間に開発する「お手軽ゲーム」ではなく、開発費を投じて高度なシステムを採用し、大量のユーザーを集める時代になってきたことがわかるゲームでもある。
不満ながらも止めない理由
ただ、遊んでいると楽しい半面、フラストレーションがたまることも多い。
例えば、ゲーム中に友人を勧誘するメールを出させようとしたり、有料アイテムを買わせようと誘導したりする仕掛けがしばしば現れる。アイテム課金モデルである以上、仕方ないとはいえ、ゲームを進めるうえで必要なアイテムは常に不足している。長い時間をかければ無料で入手することもできるが、早く先に進むには結局、有料アイテムを買うしかない。
1つの命令を出してから、次の新しい命令を出すタイミングがくるまで5分、10分、30分と一定の時間待つ必要があることも不満の理由だ。普通のゲームのようにどんどん先に進むことができず、繰り返しアクセスする手間をかけなければならない。
そのせいで仕事がはかどらず、もう何度も「やめよう」と思った。それでも止めないのは、ゲームが進行すると何か大きなことを達成したような気分を味わえるからだ。画面をついつい眺めて新しい命令を出すタイミングを待ったり、有料アイテムを使ったりする。他のソーシャルゲームでも同様の経験を持つユーザーは少なくないだろう。
このようにソーシャルゲームには、ユーザーが不満を感じつつも「お金」と「時間」をつい使ってしまう要素がある。お金は毎月の明細書を見ればまだチェックできるが、困るのは時間だ。
ソーシャルゲームで遊んでいると、1日の生活時間を細切れに使うことになる。これが曲者で、全体ではかなりの時間を奪われる。にもかかわらずユーザーが離脱せず増え続けているのは、あらかじめユーザーの限界を予測して、ゲーム内容に織り込んでいるからだろう。
統計手法で顧客の行動を予測

顧客の行動や商品・サービスの市場価値は、コンピューターの発達により統計的に予測することが可能になってきている。「その数学が戦略を決める」(イアン・エアーズ著、文藝春秋)を読むと、こうした手法がネット書店からスーパーマーケットの割引、航空会社のマイルシステムまでさまざまな分野で使われていることがわかる。
例えばカジノ経営の米ハラーズは、「顧客を逃がさずにどこまでお金を搾り取れるかについて、実に高度な予測を使っている」という。スロットマシンなどの使用状況や勝ち負けなどをリアルタイムで監視し、その顧客の年齢や居住地の平均年収といったデータと組み合わせて分析する。これにより、顧客がお金をすっても楽しんでまた来店するのはいくらまでかを予測し、「この魔法の損失額数値を『痛みポイント』と呼んでいる」(46ページ)という。
このカジノでは、顧客が痛みポイントに近づくと、店のおごりでレストランに案内するといったこともしているそうだ。これについて著者は、「(中毒性もあり身の破滅につながりかねないギャンブルを)ハラーズ社がさらに心地よくしようとしていることには困惑を覚える。でもハラーズの痛みポイント予測のおかげで、顧客の幸せ度はおおむね上がる」(47ページ)と述べている。
ジンガがこうした統計的手法をCityVilleで使っているかどうかは不明だが、ユーザー行動を追跡して予測に利用する技術がエンターテインメント分野に広がっているのは間違いない。
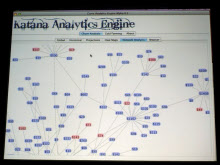
米サンフランシスコで10年3月に開催された「ゲーム開発者会議」で、南カリフォルニア大学のドミトリ・ウィリアム准教授は、「Katana Analytics Engine」というユーザー行動分析ツールを公開した。これは、パソコン向けオンラインゲームの特定ユーザーが他のユーザーとどのような関係にあり、その存在がどれだけの経済価値を生むかを「ドル」表示するというものだ。
このツールはライセンス販売されており、ソーシャルゲームでも一部企業のサービスで使われ始めている。しかし、こうした分析は合理的と思う半面、どこまで許されるか割り切れない部分も残る。
「過剰な刺激」がもたらす危険
カリフォルニア工科大学生物学部の下條信輔教授は著書の「サブリミナル・インパクト」(ちくま新書)で、「(現代は)情動脳、社会脳を含む神経系全体の活性化を目指す大きな潮流の時代」と指摘している。リアル、バーチャルを問わず、人間の神経系を揺さぶるような過剰な刺激で働きかけ、それをマーケティングなどに活用する動きが進んでいるという意味だ。
これはゲームだけを指すわけではないが、刺激の増大と加速は最終的には「破断点」にたどり着く危険があると著者は警告する。同じような議論はゲーム機がブームになった80年代以降、何度か起きている。しかし、ゲームがクラウド型のサービスに移行しつつある現在、ユーザー行動の分析はより容易になり、サービスのバリエーションも過去にないほど広がろうとしている。
2月26日に発売予定の「ニンテンドー3DS」や近く発表になるとみられる「プレイステーション・ポータブル」の新型機も、どのような形であれ、インターネットを利用した「ソーシャル機能」が目玉の1つになるはずだ。企業が痛みポイントを探る重要性はさらに増し、この流れは止められない。
しかし、こうした現象が社会に浸透することには、拭いきれない不安がある。ソーシャルゲームを遊びながら、ある種の「薄気味悪さ」を感じるユーザーは筆者一人ではないのではないか。
1970年生まれ。慶應義塾大学商学部及び環境情報学部卒。ゲーム会社で営業、企画職を経験後、ゲーム産業を中心としたジャーナリストに。国際ゲーム開発者協会日本(igda日本)代表、立命館大学映像学部非常勤講師、日本デジタルゲーム学会(digrajapan)理事なども務める。











