2014.01.31
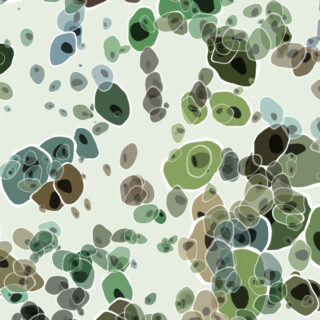
なぜSTAP細胞は驚くべき発見なのか――STAP細胞が映し出すもの
はやいもので、2014年最初の月はもう終わろうとしている、しかし、そのひと月だけでも、幹細胞研究やがん研究に関するニュースがいくつか報じられていた。
・小分子RNAによって悪性度の高いがんを正常な細胞に転換させる (鳥取大)
・神経幹細胞の分化制御に関わる小分子RNAを特定 (慶應・理研)
・化合物を加えてiPS細胞に似た集団を得る (京都大)
だが1月最終週になって、とんでもない報告が飛び出すことになった。それが、理化学研究所・発生再生科学総合研究センター(理研CDB)のグループリーダー、小保方晴子博士らによる「STAP細胞」の報告である。
多能性を再起動させる
STAPというのは「Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency」の略。日本語では刺激惹起性多能性獲得細胞、と名づけられているそうだが、ようするに、「とある細胞に刺激をあたえたら、身体を構成するあらゆる種類の細胞になる能力を身につけちゃった」、ということだ。これは、京都大・山中伸弥教授とイギリスのジョン・ガードン博士がノーベル賞を受賞したこととも大きく関係する。
2012年、山中教授らに与えられたノーベル賞は「体細胞のリプログラミング(初期化)による多能性獲得の発見」というのが受賞理由になっている。
ヒトを含む動物は、受精卵という1つの細胞から出発して、60~100兆個、体内でさまざまな役割をはたす250種類程度の「体細胞」へと分裂・分化していく。そして、いったん分化しきってしまえばそれっきりで、後戻りはできないというのが常識になっていた。それを覆すきっかけを作ったのがガードン博士であり、完全に打ち崩したのが山中教授であった。彼らの研究が高く評価されたのは、細胞のゲノムには受精卵のような性質、つまり「多能性」という能力を発揮するためのシステムは残されていること、そしてそのシステムを再起動させる方法を見出したことによる。
ガードン教授は卵細胞に、体細胞のコアである「核」を移植し、卵細胞が持っているリセット能力を利用した。また、山中教授はウイルスによって体細胞に遺伝子を組み込み、システムを再起動させるリセットスイッチを新しく作ったのである。すなわち、もともとの体細胞の中でつくられていない部品を利用したのである。
STAP細胞は「多能」ではなく「全能」?――iPS細胞との違い
STAP細胞は新たに外部から何かを付け足すのでもなく、細胞自身のシステムを再起動してみせた。小保方博士らは、以前の論文で、微細なガラス管体を用いて「選別」された細胞が「多能性を持っている」ことを報告していた。ただ、博士の記者会見などによれば、それは細胞を「選別」しているのではなく、細胞にとって一過的に窮屈な環境が作られること、つまり細胞に物理的なストレスが加えられることがトリガーとなって、内在的な多能性システムが活性化、つまり「初期化」されているのではないかと考えたという。
細胞にストレスを与えるにはどうすればよいのか。それを検討した結果、pH5.7(オレンジジュースでpH4くらい)――体の組織としてはなんていうことのない、しかし細胞が単体で生きるには「ほぼ致死量」にあたる――という酸性条件で25分間置く、という条件へとたどり着いた。
その結果、生後1週目のマウスから脾臓の中にある、白血球系統に分化した細胞を酸性条件で処理し、iPS細胞などと同様の培養液で7日間培養することで、体内にある様々な能力を持った細胞ができるとことが示された。さらには脳や皮膚、骨格筋、脂肪組織、骨髄、肺、肝臓、心筋といった組織の細胞でも、同様の性質の細胞を得られた。さらに、細胞膜に穴をあけるストレプトリシンOという細胞毒素で処理をしたりすることでも、頻度の違いはあれど同様の細胞が得られているという。
こうして得られた細胞を詳細に解析すると、ゲノムの状態は多能性に関連するシステムのスイッチが入った状態になっていた。さらにユニークな点でいえば、STAP細胞はこれまで多能性を持つ細胞の代表例として知られていたiPS細胞やES細胞と違い、胎盤は羊膜にも変化しうることが示されている。iPS細胞やES細胞は、基本的には体をつくるどんな細胞にでもなれるが、胎児を包む羊膜や、母胎とのジョイントシステムである胎盤には変化できないがゆえに「全能」ではなく「多能」と呼ばれてきたのである。
ただし、STAP細胞自体は、「幹細胞」という存在とは少し異なった存在である。幹細胞とは、前述の「いろんな細胞を作り出せる能力」(分化能)だけでなく、「自分と同じ能力を持った細胞を作り出す能力」(自己複製能)を持たなければならない。iPS細胞もES細胞もこうした条件を満たしているが、STAP細胞は試験管の中では、細胞分裂をして増殖することがほとんど起きない。しかし、ACTHというホルモンを培養液に加えてやると、STAP細胞は増殖を開始し、自己複製ができることが示されたほか、面白いことに、この細胞では胎盤などの細胞を作り出す能力が失われることも示されている。
これとは対照的に、STAP細胞の状態でFgf4というタンパク質を培地に加えると、ACTHの場合とは逆で体の細胞を造る能力が失われ、胎盤や羊膜にしか変化できなくなったのである。こうした性質は、今後のiPS細胞研究、そしてES細胞研究に大きなフィードバックを与えてくれるだろう。
細胞は物質によって操作されうる
「なかなか採択されませんでした」と小保方博士自身がコメントしていたし、「細胞生物学の歴史を愚弄するものだ」という査読者のコメントも紹介されていた。山中教授が2006年にあれほど明確な形で体細胞の初期化の可能性を示していなかったら、この論文はさらに長い間お蔵入りさせられていたかもしれない。あるいは小さな雑誌に掲載され一般には知られることもなく、遥か未来に再発見されるのを待つことになっていた可能性もある。
だが、そうした常識・先入観にくじけることなく、Oct3/4という多能性のネットワークの鍵となる遺伝子に着目した点は非常にすばらしく、それを目に見える形で(Oct3/4遺伝子が再び発現していくさまを動画が撮影されている)示したことは大きな説得力を持つ。また、さまざまなストレスでSTAP細胞が作成できること、そしてさまざまな細胞種で再現可能なこと、なによりSTAP細胞に由来する細胞のみで体を構成されるマウスが生まれることができる、というのは決定的であり、再現可能な実験であることは疑いがない。小保方博士がこうした労苦を積み重ねて査読者をねじ伏せたというのは見事というほかない。
ただ、このシステムが内在的に存在しているとはいえ、そのトリガーは酸性条件や細胞膜を溶かすという過酷な条件を用いているので、かなり人工的なもの、ということもできるだろう。しかし、冒頭で例示した業績も、翻ってみれば合成されたRNA配列を組み込む、化合物という「物質」を細胞にふりかけるということでできている。これまで、どれほど多くの知見が「それは生理的ではない」という言葉のもとに切り捨てられ、埋もれてきたことだろう。
これまで細胞がもつ多彩な能力は「わけてもわからない」とされ、「自然」とされる状態が美化されてきた。だが今回の報告から考えるに、細胞はやはり物質(環境)によって操作しうるものであり、分け入って、物質的な意味を知ることによって理解を深めゆくものであるはずだ。そうした営みは、「自然」という観点からは忌避されることも少なくないが、今回のような研究の進歩は、人間にとっての「知」とは何なのかを深く考えさせてくれる。
STAP細胞からメディアのあり方を逆照射する
STAP細胞のようなユニークな報告というのは今回に限らず、山中教授のiPS細胞報告後にもいくつか行われていた。例えば皮膚の培養細胞に乳酸菌を加えて培養すると、多能性を持つ細胞が得られる、あるいはらい菌と共培養すると神経細胞が幹細胞へとリプログラミングされるという報告もなされていたが(後者に至ってはCellというメジャーな雑誌であるにもかかわらず)、これらの報告はあまり大きくはとりあげられなかった。だが、こうした報告も合わせて、生命のシステムというのは、偶然がいくつも重なりあって、既存のシステムが寄せ集まってできた「いい加減なシステム」だからこそ冗長性があり、ヒトが介入する余地があると考えてもよいのではないだろうか。
なんにせよ、メディアはこの報告を出発点に「臨床応用」「究極の再生医療のリソース」などというわかりやすい方面にのみ論点を向けたり、「iPS細胞より優れた細胞」などという意味のない比較論に世論を誘導するという情けない結論にはたどり着かないでほしい。臨床応用というのは単純なことではない。iPS細胞はさまざまなハードルを乗り越え、はからずも小保方博士の所属する理研CDBにおいて臨床応用へと結実しようとしている。
臨床にせよ基礎科学にせよ、どちらが優れているか、というものではなく、お互いに補完しあう存在なのだ。さらに、再生医療に至る方法としては、目的の細胞を体内で直接作り出す「in vivo ダイレクトコンバージョン」や3Dプリンタなどと生体材料を組み合わせた「バイオマテリアル」、精細な目的の場所に薬剤を送り届ける「ドラッグデリバリーシステム」などのさまざまな選択やハイブリッドがあるのである。短い視点で選択肢を減らしてしまうことは、決していい結果を産まないだろう。
小保方博士が会見で述べた「100年後に貢献しうる仕事をしたい」と語ったことは、自身が持つ研究のモチベーションを如実に示している。まだ成人の細胞でSTAP細胞が樹立できるのか、ヒト細胞でそれができるのかについてはこれからの報告を待たなければならない。なにより、こうしたシステムがなぜ動くのか、マウスES/iPS細胞とヒトES/iPS細胞がどうして違うのか、胎盤と体をつくる細胞の切り替えるスイッチは何なのか。STAP細胞は、こうしたさまざまな疑問の答えのよすがとなっていくだろう。ひいては、基礎科学分野での根源的な問いである、「命はどのようにして生まれてくれるのか」に対しても、大きなピースの一つになるに違いない。
また、あまり大きく説明はなされていないが、この細胞は胎盤などへも分化しうるため、子宮内に着床してクローンになるのではないか、という懸念も浮かぶだろう。受精から発生にいたる筋道はさまざまなプロセスが必要なため、この細胞のみでは、おそらく個体発生にいたる過程をトレースすることは難しいかもしれない。だが実は、四倍体凝集法という手法を用いれば、マウスレベルではiPS細胞やES細胞のみに由来する個体を作り出すことはできている。技術的観点から、ヒトでこの方法が成功するのは時間がかかると思われるが、クローンをつくることが本当に許されないのかどうかといった観点から、既存の価値観を批判的に捉え直すことも必要になってくるはずだ。
どのみち、この論文によって号砲は放たれた。聞くところによれば、すでに理研はSTAP細胞の特許出願を済ませ、アメリカでは小保方博士らの共同研究者がコアとなって霊長類での実験が進展しつつあるという。日本初、と浮かれた論調も散見されるが、(研究倫理的に許容されることではなくとも)論文に否定的な見解を述べて却下させた査読者が、自分の研究室でヒト細胞を用いたさらにすすんだ実験を立ち上げている可能性だってある。
そして、小保方博士がなぜ若くして独立研究者の地位を勝ち得たか、どのような人事制度がそうしたことを可能にするのか。STAP細胞をめぐるメディアの報道は、なぜそれが「できないか」を逆照射するかのようなものだ。そう考えれば、割烹着を着てさまざまな細胞に酢をぶっかけろ、と研究者の尻を追い立てることがメディアや科学行政の仕事ではないことは、おのずとわかるはずである。
サムネイル「Cells」Filter Forge
http://www.flickr.com/photos/filterforge/9075324674/
翻ってみれば合成されたRNA配列を組み込む、化合物という「物質」を細胞にふりかける
プロフィール
八代嘉美
1976 年生まれ。京都大学iPS細胞研究所上廣倫理研究部門特定准教授。東京女子医科大学医科学研究所、慶應義塾大学医学部を経て現職。東京大学大学院医学系研究科博士課程修了、博士(医学)。専門は幹細胞生物学、科学技術社会論。再生医療研究の経験とSFなどの文学研究を題材に、「文化としての生命科学」の確立をを試みている。著書に『iPS細胞 世紀の技術が医療を変える』、『再生医療のしくみ』(共著)等。
