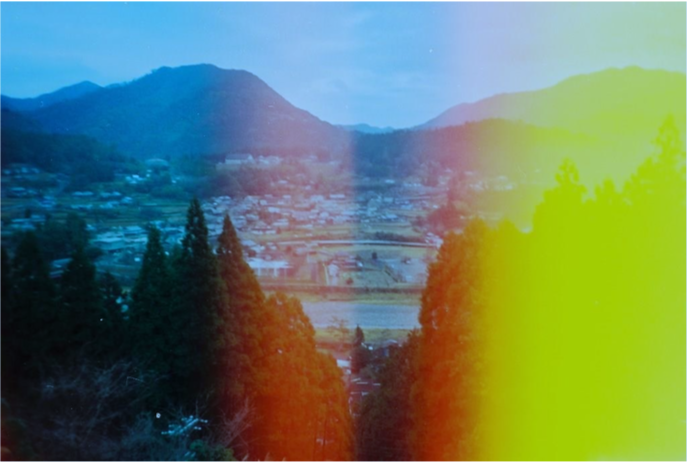書店人に告ぐ

実を言うと、僕が起業したきっかけは、消極的な理由からだった。
おそらく、これは業界全体について言えることだろうが、アルバイトから店長に抜擢され、契約社員に取り立ててもらったまではよかったのだが、なかなか、正社員にはなれなかった。
実はその当時、正社員になったら結婚しようと言っていた彼女がいたのだが、それが2年目になると、彼女はしびれを切らせるようになってきた。会えば、ケンカをするようになった。彼女は、僕の働きが悪く、無能だから社員に昇格できないのではないか、と罵るようになった。次第に、会うのが億劫になった。僕は元来、楽天的で、どうにかなるだろうと考えていた。
あの当時は、ずいぶん酷いことを言われたものだと思ったが、今では彼女の気持ちが、よくわかる。いや、彼女というよりも、女性の気持ち、と言った方が、あるいは適切なのかもしれない。
語弊を恐れずにいえば、女性は子を産み、子を育てるように、生物学的に宿命づけられている。もちろん、男性も育児に参加しなければならないが、物理的に子どもを産むのは不可能である。そういった意味で、女性は、本能的に生活能力を男性に求める傾向があるのだと思う。男性に対して、自分と産まれてくるだろう子どもを養うだけの能力がないと感じた時に、女性は、合理的には説明できないほどの、途方もない不安に苛まれるものなのだろうと思う。それだから、結果として、男性に当たるようになる。
要するに、女性をオニババ化させるのは、間違いなく、甲斐性なしの男性だということだ。
お金はすべてではないが、やはり、お金は必要なのだ。
2年間店長をしても、社員に昇格できなかった。
次第に、モチベーションも低下していった。いくら結果を残しても、給与に跳ね返ってこないからだ。いつまで経っても結婚できそうにもなかった。そして、その当時の彼女とは、結果的に別れることになった。
何かがおかしいと思った。
僕は、会社の上層部に疎まれていたわけではない。むしろ、社長にも部長たちにも、周囲が嫉妬するほどに優遇されていた。また、高く評価もされていた。
それなのに、どうして、僕は社員になれないのだろうか。
答えは、会社にあるのではなかった。ましてや、僕が甲斐性なしだったからでもなかった。この業界自体に問題があると思った。
書店の取り分は、22%〜25%程度でしかない。1000円の本が1冊売れたとしても、220円〜250円しか、粗利として残らないということだ。そこから、家賃を引き、人件費を引き、その他の経費を引くと、本当に雀の涙ほどしか利益が残らないのである。これは、他の業界ではあり得ない数値である。
計算してみて、ゾッとしたものだ。いくら、売り上げが上昇したとしても、あり得ないくらいに劇的に売り上げが上昇したとしても、この仕組みである限りは、利益はそんなに増えないのだ。魔法にでもかけられたように、利益が増えない。
書店に実に少ない利幅を押しつける、いわゆる「再販制度」というものが、当時は悪の根源のように思えた。
「結婚するには、転職するしかないよ」
以前、書店員から出版社の営業に転職した人が、そう言っていたことを思い出した。
確かに、知っている書店員も、結婚する際に転職する人が多い。理由は、家族を養っていけないからだ。
もっとも、今から考えれば、嘘のように本が売れていた時代があったという。並べておけば、ハードカバーの本が飛ぶように売れ、商品を確保するのが困難だった時期があるという。その当時の書店の社員は、それ相応にいい給料をもらっていたという。
結婚し、子供を大学に通わせることもできた。
けれども、今はどうだろうか。親の財産を当てにできるのでなければ、子供を大学に行かせるどころか、独立して結婚するのも困難である。
このまま書店にいていいのだろうか、と30を目前にして思った。これは、僕ばかりではなく、多くの書店経験者が通った道なのではないかと思う。経済的理由で、結婚を躊躇した人も中にはいるはずだ。
彼女と別れ、手元には、結婚資金として少しずつ貯めていた、わずかばかりのお金があった。軽自動車を買えば、あらかたなくなってしまうほどの金額である。家賃43000円のアパートで、切り詰めた生活をして貯めたお金だった。
ただ、結婚という当面の目標も失って、そのお金も行き場を失っていた。
結局、僕は、このお金を使って、会社を興すことに決めた。
何も知らずに足を踏み入れた、ビジネスの世界は、まるで「銃声なき戦場」だった。
そこで僕は夥しい失敗を重ね、ときに、わずかばかりの成功を経験した。
子細は省くが、戦う術を知らなかった僕は、満身に銃弾を浴びて、ふたたび、書店に戻ることになった。有り体にいえば、僕は書店に救われたのだ。
古巣に戻った僕は、当初、自分が浦島太郎になっていて、新しい書店界についていけないのではないかと危惧した。
しかし、その危惧は一瞬にしてなくなった。
また、業界は、相変わらず、旧態依然としたままだった。
まがいなりにもビジネスの世界を目の当たりにしてきた僕は、浦島太郎になったどころか、旧石器時代にタイムスリップしたのではないかという感覚に陥った。
マーケティング3.0が叫ばれている時代に、マーケティング2.0にも至っていないのが、書店業界の現状だった。
僕は、愕然とした。そして、不思議に思った。
「なぜ、このマーケティングレベルで商売をやっていられるのだろう」
僕は大学時代、スーパーでアルバイトをしていたことがある。
ここでは、魚や野菜、肉といった食料品は、もちろん、市場などから「買い切り」で仕入れてくる。当然、売れなかったからと言って、市場や問屋に返せるはずがない。自然、仕入れや売場の担当者には、緊張感が芽生える。何とかして売り切ろうという、商売人の魂が養われる。
一方、本は「返品条件付き買い切り商品」である。
本は腐るわけもなく、また他の業界にすれば信じられないことに、売れなければ、仕入れた額と同じ額で、出版社に返すことができる。自然、仕入れや売場の担当者には、緊張感が失われる。これでは、何とかして売り切ろうという、商売人の魂が、養われるはずがない。
それなのに、なぜか、商売が成り立っている。
商売人が稀な業界において、依然として商売が成り立っている。
原因は、明白だった。理由はひとつしか考えられなかった。
以前は、悪の根源だとばかり思っていた「再販制度」がこのビジネスを支えていたのだ。全国津々浦々まで雑誌を配送するために、必然的に生まれたこの制度は、考えても見れば、実に優れた制度だった。取次を中心とした、その精密緻密なシステムは、ビジネス的な視点で捉えれば、天才的とも言えた。
それは、最悪、現場にビジネスマンがいなくとも、書店業という商売が成り立たせることができる、魔法のようなシステムだった。
そう考えると、書店の低い取り分が、妥当だということがわかった。
なぜなら、ビジネスの世界では、最大のリスクを負う者が、最大の利益を得るのは至極当然なことだからだ。
この業界の場合、最大のリスクを負う出版社が最大の利益を得る構造になっているのは、そう考えれば、当然のことである。
問題は、この業界の経済を上手く回転させて成長させてきた「再販制度」が、時代にそぐわなくなってきたということだ。同じように、成立当初、あまりに優れたシステムを持ったために、長く日本を支配することになった江戸幕府のシステムが、19世紀の時代にそぐわなくなったように、「再販制度」は、今大きな修正を余儀なくされている。
繰り返すようだが、「再販制度」は実に優れたシステムである。そして、出版社が最大の利益を確保することは、ビジネス的な視点でみれば、至極当然のことである。
ならば、書店業界は、このままデフレスパイラルのようなマーケットの縮小の中で、次々と倒れて当然なのか?
僕は決して、そうだとは思わない。
出版社に対して、まるで圧力団体のようになって、利益の再分配をねだり続けるのが唯一残された道なのか?
僕は絶対に、そうだとは思わない。
ここからが本題である。
全国の「書店員」に告ぐ。
いや、聞く耳を持ち、業界の未来に今なお希望をいだく、全国の「書店人」に告ぐ。
どこかで、本が好きだからと、ボランティア精神で仕事をやっていないだろうか。
潜在的に、本を神聖視し、それに仕える殉教者のような精神を抱いていないだろうか。
本屋は稼いではいけないのだと、諦めてはいないだろうか。
もし、そうだとすれば、これをきっかけに、少し真剣に考えて欲しい。
今までは、「再販制度」というある種のバリアによって、書店は守られてきた。書店の外が、「銃声なき戦場」であることを、知らずに済んできた。それでも、真面目に働けば、ある程度の収入が得られ、まともな生活ができてきた。
だが、これからの時代は違う。
これまで事実上、書店を守ってきた「再販制度」のバリアが弱まってきている。あたかも、江戸時代の日本を外敵から守ってきた「鎖国」の効力が幕末において弱まってきたように。
ここからは、書店にいるひとりひとりが、「銃声なき戦場」、つまりはビジネスの世界で戦うために、武装しなければならない。ボランティアでもなく、文学殉教者でもなく、ビジネスマンだという気概を持たなければならない。
そう、間違いなく、書店業とはビジネスである。
また、書店人とは、本来、ビジネスマンであるべきなのだ。
その気概を持てば、はじめて、出版社に対して書店業界の衰弱を理由に利益の再分配を迫ることが、みっともないことだと言うことがわかるはずだ。
対等関係のビジネスマンなら、絶対にそんな真似はしない。
それはまるで、五体満足で心身共に健康でありながら、暮らせなくなったからと政府に生活保護をねだるのと同じである。
ビジネスマンなら、ビジネスの話をして、利益を確保すべきである。
ビジネスの話とは、「自分にはあなたのビジネスが伸張する上で、こういうプラスになることができるから、相応の利益をいただきたい」と対等に、正々堂々と相手にいうことである。
相手の利益を確保し、ともに自分の利益を確保することが、ビジネスの基本である。
相手が勝ちすぎているからと言って、ハンデをもらった時点で、それはフェアなゲームではなくなるのだ。
もっとも、出版社側が書店業界を救うためと、ある種の利益を拠出してくれる意志は、この業界を思ってのことであり、実にありがたいことである。
でも、それは、気持ちだけありがたく受け取っておこう。
それはビジネスではなく、「ほどこし」だからである。
また、自ら「ほどこし」をせがむのは、もはや、ビジネスマンですらない。
もしかして、その「ほどこし」を受けた者は延命するかもしれない。けれども、労せずして受けた「ほどこし」に慣れてしまえば、多くの場合、ビジネスマンとしての商魂がますます萎えてしまうものである。そこから新しい力強さを持った種が生まれたという歴史を、人類は知らないのではないだろうか。
あるいは、これからの時代、この業界は様々な困難に直面するかも知れない。
多くの同業者が倒れ、多くの仲間達がこの業界にいられなくなるかもしれない。
けれども、ビジネスマンとしての商魂を身にまとった強靭な意志たちは、幾多の淘汰をくぐり抜けて、
では、具体的にどうすればいいだろうか?
前年比割れは恒常化し、今こうしている間にも、全国で1日に2軒以上の書店が消えてなくなっているという現状で、いったい、自分たちに何ができるというのか?
その問題を解消するために、これからアイデアをひとつ提示しようと思う。
明日の書店業界の未来を思う、ビジネスマンとしての書店人のために、小さいながらも「希望」を用意した。
それこそが、書店の現場からベストセラーをつくるプロジェクト「CORE1000」である。
「CORE1000」とは、ベストセラーの熾火(コア)となる実売1000冊のことである。
書店の現場が、ベストセラーの火付け役になって、テレビやPR会社の後追いではなく、書店の現場にイニシアチブを奪還するためのプロジェクトであり、同時に、書店の売場を「耕し」て販売力を高め、書店がビジネスマンとしての発言力を高めるためのプロジェクトでもある。
これに参加することをきっかけとして、それぞれの書店人が、ビジネスマンとしての気概に目覚めてくれればいいと考えている。
これからは書店の時代だ。
僕がそう信じる理由を、次回、明らかにしたいと思う。
また、「CORE1000」についても、詳しく説明できればと思う。
まもなく、「CORE1000」が始動しようとしている。
書店人が本当にビジネスマンたりえるのか、試される時がきたのだと思う。
我こそはと思う書店人の方々、ぜひ、この機会を逃すことなく、参加していただければと思う。
参加することによって、この業界の明るい未来が、わずかながら垣間見えるだろう思う。
関連記事
-
【9/18(金)〜10/18(日) 京都天狼院写真展】 「KODO ‒Heartbeat of Kumano‒ 」KYOTOGRAPHIE サテライト企画 KG+で開催
-
開催延期【第2回 4/11(土)13:00〜 京都】絵本「ねこになりたい」原画展開催記念!作家山口哲司さんによる絵画教室!布に招き猫を描いて楽しもう!《初参加大歓迎!》《絵が苦手でもOK!》
-
開催延期【第1回 4/4(土)13:00〜 京都】絵本「ねこになりたい」原画展開催記念!作家山口哲司さんによる絵画教室!布に招き猫を描いて楽しもう!《初参加大歓迎!》《絵が苦手でもOK!》
-
【3/14(土)〜 4/12(日)京都天狼院2階屋根裏編集室ギャラリーにて】絵本「ねこになりたい」原画展開催!可愛らしい猫たちがみなさまをお出迎え!《入場無料!》
-
【写真展開催8/2(金)~8/25(日)】全国の高校写真部とコラボした写真展「SIMPLE DAYS 〜高校生×フィルム写真〜」 天狼院書店「東京天狼院」/アーツ千代田 3331の2会場で展示